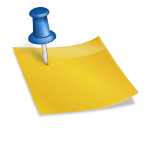高年齢者の定年と再雇用制度について
我が国の企業の定年は、長年、60歳というのが一般的でした。
しかし、2013年(H25年)以降、年金支給開始年齢が65歳以上に引き上げられることとなったことや、少子高齢化に伴い労働力が不足する状況に対処するため、高年齢者を引き続き65歳まで雇用するための施策として、定年年齢の引上げや、再雇用制度=継続雇用制度の導入が企業に義務付けられることとなりした。
高年齢者雇用確保措置とは
具体的には、高年齢者雇用確保措置として、2013年(H25年)施行の高年齢者雇用安定法第9条で次のいずれかの措置を導入することが義務付けられました。
- 65歳までの定年の引上げ
- 65歳までの継続雇用制度の導入
- 定年の廃止
上記3つの高年齢者雇用確保措置のうち、多くの企業は②継続雇用制度を採用しています。
定年の引上げや廃止の場合には、従前の労働条件を変更することは困難ですが、継続雇用制度による場合は、定年により一旦は退職した上で、再雇用という形をとるため、新たな労働条件を設定する余地があるためです。
高年齢者就業確保措置とは
更に、2021年(R3年)には、高年齢者就業確保措置として、定年を65歳以上70歳未満としている事業主や、70歳未満までの継続雇用制度を導入している事業主は、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が定められています。
- 70歳までの定年の引き上げ
- 定年制の廃止
- 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
- 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
- 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
・事業主が自ら実施する社会貢献事業
・事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
これらは努力義務ですので、現時点では、2013年に導入された高年齢者雇用確保措置が導入されていれば問題はありませんが、65歳超の継続雇用などの就業確保措置に取り組んだ企業は、助成金の給付を受けることができる場合があります。
継続雇用制度を運用する際の留意点
雇用確保措置としての継続雇用制度は、再雇用ではあるものの、通常の採用とは異なる次のような特徴があります。
① 希望者全員を継続雇用しなければならない
② 労働条件を定年前の条件と変更することは可能だが、一定の制約がある
③ グループ企業による継続雇用も選択できる
①として、継続雇用の対象者を選別することは基本的に許されず、この意味で事業主側の採用の自由は大きく制限されています。継続雇用の例外は、心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由に該当する場合に限られます。
定年後再雇用の労働条件を引き下げても良いか
一方で、②の労働条件変更は、ある程度まで柔軟に可能、という理解が一般的です。例えば、短時間勤務とすることや、勤務日数を制限すること、定年前の職務とは別の職務に従事させること、それに伴い定年前の給与体系とは異なる給与の条件とすることなども可能です。
とはいえ、定年後再雇用の条件も一定のレベルを保つ必要があります。
例えば、賃金が従前の25%、勤務日数が週に3,4日と提示された事案で、裁判所は、再雇用の際に「極めて不合理であって,労働者である高年齢者の希望・期待に著しく反し,到底受け入れ難いような労働条件を提示する行為」は、「継続雇用制度の導入の趣旨に違反した違法性を有する」とし、高年齢者が65歳までの安定的雇用を享受できるという「法的保護に値する利益を侵害する不法行為」となることを前提に、「定年の前後における労働条件の継続性・連続性が一定程度,確保されること」が原則として求められるとし、「定年退職前のものとの継続性・連続性に欠ける(あるいはそれが乏しい)労働条件の提示が継続雇用制度の下で許容されるためには,同提示を正当化する合理的な理由が存することが必要」として、この事案では慰謝料100万円を認めています。
また、継続雇用制度として、再雇用後は1年を契約期間とする有期嘱託社員とし、1年ごとに契約を更新するという形がとられることが多いです。更新に一定の条件を付すことも可能で、再雇用の嘱託社員に契約更新のために努力する動機付けとなります。
定年後再雇用の従業員の契約更新を拒否することの可否
継続雇用制度の導入により定年に達した従業員を有期嘱託社員として採用した後に、能力不足や勤務態度に問題があるなどの理由で契約の更新を拒否することはできるでしょうか。
継続雇用の対象から外すことができるのが解雇事由・退職事由に該当する場合に限られることもあり、更新拒否も、自由にこれを行うことができるわけではありません。
定年後の継続雇用も、有期労働契約に一般に適用されるいわゆる『雇止め法理』による制約を受けます。
定年後再雇用での「雇止め法理」とは
雇用契約の期間を定め、契約期間が満了した場合であっても、一定の要件を満たした契約においては、契約更新を拒否できないとされており、これを「雇止め法理」と言います(労働契約法19条)。
雇止め法理は、実質無期契約型(同法19条1号)と期待保護型(同2号)に区別されます。
実質無期契約型は、業務の客観的内容、当事者の主観的態様、更新手続の態様などの諸般の事情から、期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態に至っていると同視できる類型です。
一方、期待保護型は、業務内容の恒常性や当事者間の言動・認識などから、労働者の側に雇用継続への合理的な期待が認められる類型を言います。
いずれの類型でも、客観的合理性・社会的相当性を欠く更新拒絶は許されないという制約に服することになります。これに違反した雇止めは違法無効とされ、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で労働契約が存続するものとして扱われます。
再雇用後の従業員の契約更新を拒否する際には、この雇止め法理の適用により、更新拒否が許されない状態か否かを検討する必要があり、高年齢者雇用安定法により65歳までの雇用確保措置が企業に義務付けられたこととの関係で、一般的に『65歳に至るまでの雇用継続への合理的な期待』が認められやすく、「期待保護型」とされる可能性が高いと思われます。
そのため、再雇用後の従業員の更新拒否は、雇止めとすることを正当化するだけの客観的合理性と社会的相当性を備えることが必要となります。雇止めとする前に、その根拠資料の収集などが必要となります。
雇止めが無効となった判例【津田電計計器事件(最判平成24年11月29日・労判1064号13頁)】
定年後再雇用され、1年間の有期嘱託契約により雇用された従業員が、1年間経過後に契約更新を拒絶されたことは無効であるとして、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認等を求めた事案です。
裁判所は、当該従業員の「在職中の業務実態及び業務能力に係る査定等の内容」が「所定の継続雇用基準を満たすものであった」ことを前提に、「雇用が継続されるものと期待することには合理的な理由があると認められる」としました。更に、会社が、継続雇用基準を満たしていないものとして本件規程に基づく再雇用をすることなく嘱託雇用契約の終期の到来により雇用が終了したとすることは、「他にこれをやむを得ないものとみるべき特段の事情もうかがわれない以上,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない」としました。
一定の継続雇用基準を設けた以上、これに従って継続雇用の可否を判断することが必要となります。基準策定に際して、企業は慎重に検討をしなければなりません。
定年後再雇用の問題、その制度設計などは弁護士にご相談を
当事務所では、定年後再雇用の有期嘱託社員について雇止めをしようとする場合、その企業によって異なる個別具体的な事情を踏まえて、どのように判断すべきかということについて助言・指導をしております。場合によっては、制度設計から見直すべきケースもあります。いずれも、トラブル回避、紛争回避といった観点が必要で、特に使用者側で労働事件に取り組んできた弁護士として、経験に裏打ちされた実務的な対応を得意としています。
お気軽にご相談ください。
2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。
※日本全国からのご相談に対応しております。