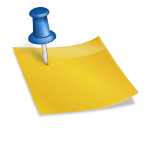1. はじめに
労災保険(労働者災害補償保険)は、従業員が業務上の事由により、ケガ・病気・障害を負ったり、死亡した場合に適用される保険制度です。本来、会社としても従業員の健康や安全を守るために、労災認定に協力する立場にあります。
しかし、実際の現場では「これは本当に業務上の事故・疾病なのか」「会社側に過失がないのではないか」といった疑問を抱えるケースも珍しくありません。とりわけ、会社としては労災とは考えていないにもかかわらず、従業員やその遺族が独自に労災申請を行うことも十分にあり得ます。そのようなとき、会社はどのような対応をとればよいのでしょうか?
本コラムでは、「会社側対応」の視点から、労災申請の際に会社が負う義務や、事業主証明欄への記載方法、さらには労災審査への意見申出の手続き、そして労災認定後に万一訴訟になった場合の対処までを時系列で解説します。
2. 労災申請とは? 会社側が「労災ではない」と考えるケースでも協力は必要?
2-1. 労災申請の基本フロー
従業員またはその遺族が、業務上の事故や疾病によって休業補償や遺族補償などを受けたい場合、所轄の労働基準監督署に対して労災の給付申請を行うことになります。通常、療養補償給付や休業補償給付を請求する際は、「様式第5号」や「様式第7号」などの書類に必要事項を記入し、会社側の証明を受けた上で提出します。
2-2. 会社の助力と証明の義務と実務上の誤解
「会社としては労災と考えていない」「従業員の自己責任だろう」という思いがある場合でも、会社には申請に助力する義務があります(労災保険法施行規則)。これを拒否すると、後に「会社が正当な理由なく手続きを妨げた」と判断されるおそれがあり、会社の信用を損なうだけでなく、監督署の調査等で不利になる可能性もあります。
したがって、「労災ではない」と感じたとしても、被害者側の申請を窓口としてサポートするという対応は必要とされる点に留意してください。
また、休業補償給付においては、「負傷又は発病の年月日」や「災害の原因及びその発生状況」等について事業主の証明を受けなければならないとされるなど、一定の事実関係について証明する責任もあります。但し、この点については、後述のように慎重な対応が求められます。
3. 事業主証明欄への署名・押印を求められた場合の対応
3-1. 事業主証明欄の役割
労災申請書類には、事業主が「その従業員が確かに自社で働いていた」「事故発生状況はこういうものであった」などを証明する欄があります。これを「事業主証明欄」と呼び、会社はそこに署名・押印することで、書類の信頼性を担保する役割を担っています。
3-2. 「会社側は労災とは思っていない」場合の具体的対応
「社内調査をした結果、業務外の可能性が高い」などと考えている場合にまで、被害者側が主張する労災事故発生の経緯について会社側証明の署名や押印を拒否できないということではありません。仮に、証明欄に署名・押印をしてしまうと、後日、会社側は記載された内容を事実と認めたものと取り扱われる可能性が高いからです。そこで、仮に署名・押印を行うとしても、そこに会社側として認められる限度の正確な事実が記載されていることを確認した上で、署名・押印を行うべきです。
例えば、事故が発生した日時や場所、業務内容などに関しては、会社が把握している限りの事実を記入して証明しても差支えはないでしょう。
一方で、意見や疑問点については、別途添付する方法で主張することが肝要です。
もし会社として異論や疑問を持っているために、被害者側が記述した事実関係については証明ができないという見解の場合には、証明を拒絶する理由を記載した文書を添付するなどして、一定の助力をしつつ、会社側の見解を明確にしておくことが必要です。
3-3. 証明欄の記載を拒否するリスク
なお、会社側が事業主証明欄への記載や押印を拒否すると、労災保険の給付申請手続きが滞り、従業員が適切な補償を受ける機会を失うかもしれません。これにより従業員との関係が悪化したり、労働基準監督署から「不誠実な対応」とみなされるリスクが高まります。後々、「安全配慮義務違反」などが争点になった場合に大きな不利益を被る恐れもあるため、一定の事実についてのみ証明を行うといった形で全面拒否の対応を避けることも、賢明な対応といえるでしょう。
4. 労災審査における会社側の「意見申出」について
4-1. 労災の審査プロセス
労災が疑われる事案について、最終的に「業務上か否か」を判断するのは労働基準監督署です。監督署は、従業員側の申請書類だけでなく、会社側の報告・関係書類・ヒアリングなどを総合的に検討して「支給・不支給」を決定します。
4-2. 意見申出を行うメリット
会社が「業務上ではない」と感じる場合は、監督署の審査過程で**「意見申出」**を行うことができます。これは、「当社としてはこう考えている」「この事故の背景には私的な理由がある」「従業員側にも重大な過失があるのではないか」など、会社が持つ事実関係や見解を提出する手続きです。
-
会社の正当性を訴える場
申請書には被災従業員の主張が中心に書かれているため、会社側の見解を伝えることは、判断に大きく影響する可能性があります。 -
証拠書類とともに提出する
作業手順書、勤怠管理記録、事故当日の業務指示内容など、会社に有利な証拠があれば積極的に提出することで、自社の主張を裏付けることができます。
4-3. 注意点:不十分な意見申出は逆効果
ただし、意見申出を行う場合も、主観的な感想や推測だけを並べるのは逆効果です。あくまで「実際に起きたこと」「具体的な文書」や「客観的事実」をもとに、論理的に整理して伝える必要があります。また、提出期限や書類の形式など、監督署の指示に従いながら適切に行うことが大切です。
5. 労災認定後、被害者側(遺族含む)が会社を訴えた場合の対応
5-1. 労災認定は「民事上の責任」を確定させるものではない
「労災」として認定されたからといって、直ちに会社の過失が確定したわけではありません。労災保険法上の「業務上の事故・傷病」として認められただけであり、それが民事訴訟における会社の損害賠償責任を自動的に確定させるわけではないのです。しかし、実務的には、監督署が労災と認めた事実が大きく取り上げられ、被害者側(遺族含む)が会社の安全配慮義務違反を主張して訴えてくるケースがよく見られます。
5-2. 訴訟の争点:安全配慮義務の有無と因果関係
被害者側が会社を訴える際の主な争点は、次のようになります。
-
会社の安全配慮義務違反
-
十分な安全対策・指導をしていなかったのではないか
-
長時間労働や無理な業務を強いていなかったか
-
-
損害と会社の行為との因果関係
-
会社の不手際が原因でケガ・死亡が発生したのか
-
従業員側の体質や私的要因が大きかったのではないか
-
5-3. 会社側として取るべき防御策
-
事故発生時の記録・証拠保全
事故発生直後から、目撃証言や写真、作業手順書、勤怠記録などを適切に保全しておくことが大切です。訴訟での立証において大きな役割を果たします。 -
適切な労働時間管理と安全衛生管理
訴訟では、会社の日頃の管理体制そのものが問題視されることが少なくありません。各種記録や指示体制を整備しておくことで、裁判でも「適切な管理をしていた」と主張しやすくなります。 -
早期に弁護士へ相談する
**「労災」問題に精通した「弁護士」**であれば、適切な争点整理や証拠の収集方法をアドバイスしてくれます。初動を誤ると不利になるケースも多いため、早めに法的専門家を交えて対処することが重要です。
6. まとめ
「労災」は、従業員を保護するための公的保険制度であり、会社にはその手続に対して助力する義務が課せられています。一方で、会社として「労災ではない」と考えている場合には、事業主証明欄への署名・押印による証明には慎重に対応し、会社側としては「業務上とは思えない」という意見や会社側が確認した事実関係を表明するという選択を行うことも検討する必要があります。
また、労働基準監督署の審査で「労災」として認定された場合でも、それが自動的に会社の民事責任を確定させるわけではありません。しかし、認定の事実を踏まえ、被害者側(遺族含む)が会社の安全配慮義務違反を訴えてくるケースは現実に多く存在します。そうした訴訟に備え、会社側は「会社側対応」として、事故の発生直後からの証拠保全、適正な労務管理・安全衛生管理の履行、そして早期の弁護士への相談が欠かせません。
-
労災申請が行われたら:事業主証明欄の署名・押印には慎重に対応、事実関係は正確に記載する
-
会社側の異論・疑問がある場合:意見申出書や添付資料を通じて労働基準監督署へ伝える
-
労災認定後に訴えられたら:安全配慮義務の有無や因果関係が争点となるため、早期に弁護士へ相談し、証拠保全や争点整理を徹底する
このように、従業員の死亡・傷害に関する「労災」申請や支給決定があった場合、会社としては冷静かつ慎重に対応することが求められます。的確な「会社側対応」を図ることで、不当なリスクを回避し、トラブルの長期化を防ぐことができるでしょう。もし疑問や不安を感じる場面があれば、早めに専門の弁護士**や社会保険労務士等にご相談ください。それが、会社の正当な権利を守りつつ、従業員や遺族との紛争拡大を防ぐ最善策となるはずです。
2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。
※日本全国からのご相談に対応しております。
-
弁護士法人本江法律事務所 弁護士 本江 嘉将https://www.motoe-law.jp/author/motoe-law/
-
弁護士法人本江法律事務所 弁護士 本江 嘉将https://www.motoe-law.jp/author/motoe-law/
-
弁護士法人本江法律事務所 弁護士 本江 嘉将https://www.motoe-law.jp/author/motoe-law/
-
弁護士法人本江法律事務所 弁護士 本江 嘉将https://www.motoe-law.jp/author/motoe-law/