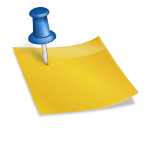1.競業避止義務とは
競業避止義務とは、従業員が在職中および退職後において、自己または第三者の利益のために、直接的または間接的に、自己の所属していた会社と同種の事業を行わない義務を指します。この義務は、企業の営業秘密や顧客情報を保護し、退職後の不正な競争を防ぐことを目的としています。
2.退職後の競業避止義務が認められるには
退職後の競業避止義務を有効にするためには、就業規則や雇用契約に定めているだけでは不十分なケースが多く、実務上は注意が必要です。福岡などの地域を問わず、日本全国で発生しうる問題であり、裁判例でも厳格に判断されます。
1. 就業規則や雇用契約に定めることの限界
- 就業規則の効力:
就業規則は、従業員が在職中に適用されるルールであり、原則として退職後の行動を拘束する効力は弱いとされています。裁判例でも、「就業規則の規定だけでは、退職後の競業避止義務を当然に課すものとはならない」と判断されることが多いです。 - 雇用契約の効力:
雇用契約に競業避止義務の条項を含めることは可能ですが、契約の効力は雇用関係が継続している間が基本です。そのため、退職後に義務を課す場合は、合理的な理由と制約の範囲が明確であることが求められます。
2. 退職時に合意書・誓約書を取り交わすことの重要性
就業規則や雇用契約だけでは不十分とされるケースが多いため、退職時に個別の合意書・誓約書を取り交わすことが望ましいとされています。
これは、競業避止義務の効力を判断する際、退職する従業員の従前の地位や業務内容などが具体的に考慮されることとの関係で、どの程度の競業避止義務について合意したのであれば相当と言えるかをケースバイケースで考える必要があるためです。
- 合意書・誓約書の役割
退職時に競業避止義務について明確に合意し、対象となる職種・業務内容・期間・地域・違反時の制裁(例えば損害賠償や違約金)などを明確に定めることで、後の法的紛争を回避しやすくなります。 - 裁判例の傾向
競業避止義務の有効性を争った裁判では、「退職時に本人が同意した書面」があるかどうかが重視される傾向にあります。
特に、退職後の競業避止義務は、従業員の職業選択の自由を制限することになるため、従業員の権利利益を侵害することを正当化できるかということの判断に、「退職時に改めて合意したか」が重要なポイントとされています。
3. 退職時の合意がない場合のリスク
退職時に合意を得ず、単に就業規則や雇用契約の記載のみで競業避止義務を主張した場合、以下のようなリスクが発生する可能性があります。
- 裁判で無効とされる可能性が高まる
裁判において、「退職後の制約について明確な同意がなかった」と認定され、退職前の競業避止義務に関する合意だけでは退職後の競業避止義務違反に関する主張が認められない可能性が高くなります。 - 合理性が認められにくくなる
競業避止義務は業務上の必要性に基づいていることにより合理性が認められるのですが、そもそも退職後の競業避止義務について明示的に定めがないのであれば、そもそも競業避止義務を課すこと自体に合理性が認められるとの評価が得られにくくなります。
3.退職後の競業避止義務が有効となる要件
退職後の競業避止義務が有効と認められるためには、企業(使用者)の利益を保護しつつ、従業員の職業選択の自由を過度に制限しないように設計する必要があります。裁判例の傾向を踏まえると、以下の点が適切に考慮されているかが重要なポイントとなります。
1. 守るべき使用者側の利益
競業避止義務が正当化されるためには、企業が保護すべき「正当な利益」があることが前提となります。具体的には以下のようなものが挙げられます。
- 営業秘密の保護
顧客名簿、価格設定、製造ノウハウ、営業戦略など、企業独自の情報を不正に利用されることを防ぐ。 - 顧客関係の維持
元従業員が退職後に顧客を引き抜くことにより、企業が大きな損害を被るリスクを回避する。 - 企業ブランド・信用の保護
競業他社への転職や独立によって、会社のブランドや信用が損なわれることを防ぐ。 - 特別な技術や知識の流出防止
特定の専門技術や開発能力を持つ従業員が、競争相手にノウハウを持ち込むことを防ぐ。
これらの利益を守るために、競業避止義務が合理的な範囲で認められるかどうかが判断されます。
2. 競業避止義務を課す従業員の地位
すべての従業員に対して競業避止義務を一律に課すことは、職業選択の自由の観点から問題視される可能性があります。そのため、義務を課す対象となる従業員の地位や職務内容を慎重に選定する必要があります。
-
義務を課しやすい従業員の例
- 企業の経営陣や役員(取締役・執行役員など)
- 営業幹部(重要な顧客との関係を持つ管理職)
- 研究・開発職(高度な技術・ノウハウを有する者)
- 戦略部門(企業の経営戦略を知る者)
-
義務を課すことが難しい従業員の例
- 一般の事務職員
- 営業アシスタント
- 製造現場の一般作業員
このように、企業の機密情報や顧客情報にアクセスできる従業員に対して競業避止義務を課すことが、合理性の観点から求められます。
3. 地域的な限定を付すべきか
競業避止義務の有効性を高めるためには、地域的な限定を適切に設定することが必要です。特に、全国規模の制限は裁判で無効と判断されるケースが多いため、慎重な設定が求められます。
-
合理的な地域的制限の例
- 企業の営業エリアに限定(例:福岡県内のみ)
- 主要な顧客が集中する地域に限定(例:福岡市・北九州市)
- 事業所のある地域に限定(例:退職者の勤務地周辺のみ)
-
無効とされる可能性のある制限
- 「全国一律禁止」
- 「海外も含めた無制限の競業禁止」
このように、実際の事業範囲に即した地域的制約を設定することが重要となります。
4. 競業避止義務の存続期間
競業避止義務の存続期間は、合理的な範囲に設定する必要があります。一般的には「1~2年」程度が妥当とされています。
-
合理的な期間の例
- 企業の競争力を守るために必要な期間(例:1年~2年)
- 技術革新のサイクルに基づく期間(例:研究開発職なら2年)
-
無効とされる可能性のある期間
- 3年以上の長期にわたる競業禁止(特に補償がない場合)
- 期限なしの競業禁止
裁判例においても、長期間にわたる競業避止義務は職業選択の自由を過度に制限するとして、無効と判断されることが多いです。
5. 禁止される競業行為の範囲
競業避止義務が適用される「競業行為」の範囲を適切に限定することが必要です。業種や職種を細かく特定することで、裁判でも有効性が認められやすくなります。
-
合理的な競業行為の制限
- 特定の業種・業務に限定(例:「自社と同業のITシステム開発業務」など)
- 特定の競合企業に限定(例:「○○社・△△社への転職禁止」)
-
無効とされる可能性のある制限
- あらゆる職種・業種での競業禁止(例:「どんな仕事でも競業禁止」)
- 不明確な定義(例:「当社と類似する業務を禁止」など曖昧な表現)
具体的な競業行為を限定することで、過度な制約を避けつつ、企業の正当な利益を保護することが可能になります。
6. 代償措置の必要性とその内容
競業避止義務を課す場合、従業員の職業選択の自由を制限することになるため、代償措置(補償)を設けることが望ましいとされています。特に、競業避止義務の範囲が広いほど、補償の必要性が高くなると考えられます。
-
合理的な代償措置の例
- 退職金の上乗せ(例:「競業避止義務に応じた追加退職金の支給」)
- 一定期間の給与補償(例:「競業避止義務期間中の収入補償」)
- 再就職支援(例:「転職先の紹介や支援金の支給」)
-
無効とされる可能性のあるケース
- 代償措置が全くない場合(特に長期間の競業禁止)
- 形だけの補償で実質的に意味がない場合
裁判例においても、代償措置があるかどうかは競業避止義務の有効性判断に大きく影響するため、適切な補償を設けることが重要です。
4.競業避止義務違反に対する損害賠償請求の内容
競業避止義務に違反して元従業員が競争相手に転職したり、独立して競業行為を行った場合、企業は損害賠償請求を行うことができます。その際、主に「逸失利益の賠償」や「違約金の請求」が問題となります。以下、それぞれの計算方法や注意点について詳しく解説します。
1. 逸失利益の計算方法
競業避止義務違反によって企業が被った損害のうち、特に**「逸失利益」**(本来得られたはずの利益)を請求するケースが多いです。逸失利益を算出するには、以下のような計算方法を用いることが一般的です。
(1) 顧客流出による逸失利益の計算
元従業員が競業行為を行ったことにより、自社の顧客が奪われた場合、その顧客からの売上や利益が失われるため、以下のような計算が可能です。
逸失利益 = 競業行為により流出した顧客の売上 × 自社の営業利益率
例えば、
- 流出した顧客の売上:年間1,000万円
- 自社の営業利益率:30%
この場合、1,000万円 × 30% = 300万円が逸失利益となり、この額を損害賠償請求できる可能性があります。
(2) 元従業員の行為による影響の算定
競業避止義務違反がなければ、その元従業員が獲得していたはずの売上を基に計算する方法もあります。例えば、
逸失利益 = 退職前の担当売上 × 営業利益率 × 影響期間
- 退職前の担当売上:年間2,000万円
- 営業利益率:25%
- 影響期間:2年
この場合、2,000万円 × 25% × 2年 = 1,000万円が逸失利益として計算されます。
2. 逸失利益を計算する際の対象期間の考え方
逸失利益を請求する期間は、競業避止義務の存続期間と同じか、それに準じた合理的な期間で設定するのが原則です。ただし、顧客が完全に定着してしまい、その後の取引復帰が見込めないなどの特殊事情がある場合は、延長が認められることもあります。
(1) 競業避止義務の存続期間
競業避止義務が1年間であれば、基本的に逸失利益の計算対象期間も1年間となるのが一般的です。
例:競業避止義務期間が1年 → 逸失利益の請求期間も1年
ただし、義務違反によって顧客が定着し、損害が長期にわたると認められる場合には、それ以上の期間についても認められる可能性があります。
(2) 裁判例の傾向
裁判では、競業避止義務の対象期間を超えた長期の逸失利益を認めることは慎重に判断されます。例えば、義務期間が2年である場合、基本的には2年間までの逸失利益しか認められないことが一般的です。
(3) 影響が続く場合の考慮
- 競業避止義務期間中に顧客を奪われ、その後も取引が戻らない場合、影響の継続性を証明することで期間延長の可能性がある。
- ただし、証拠(顧客の証言、売上データの推移など)が必要となる。
3. 違約金を定めるときの注意点
競業避止義務違反を防止するために、あらかじめ違約金を契約に定めておくことも有効です。ただし、違約金の設定が過度に高額だと、公序良俗違反として無効になる可能性があるため、適正な設定が求められます。
(1) 違約金の設定方法
- 合理的な範囲で設定する(例:退職前の年収の1年分など)
- 実際の損害額と釣り合う金額にする
- 無制限に高額な違約金を設定しない(裁判で減額される可能性が高い)
(2) 過去の裁判例から学ぶ
裁判例では、違約金を退職前の給与の2~3倍程度に設定していた場合には比較的有効と判断された事例があります。一方で、**違約金が過度に高額(退職前の給与の10倍など)**である場合には無効と判断された例もあります。
(3) 代償措置の有無との関係
競業避止義務違反の違約金を有効にするためには、代償措置(補償)を適切に設けることが望ましいとされています。たとえば、
- 競業避止義務期間中の一定額の手当を支給する
- 退職金に加えて補償金を支払う
このような措置があれば、違約金の正当性も増し、裁判でも認められやすくなります。
5.よくある質問(FAQ)
Q1. 就業規則で「退職後3年間は同業他社への転職を禁止」と定めていますが、有効ですか?
A. 一概には言えませんが、3年間という長期にわたる制限に加え、代償措置(補償)がない場合は、裁判で無効と判断されるリスクがあります。期間や補償のバランスを見直す必要があります。
Q2. 一般職の社員にも一律で競業避止義務を課したいのですが、問題ないでしょうか?
A. 企業の営業秘密や顧客情報に直接アクセスしていない社員にまで一律で課すと、過度な職業制限として無効となる可能性があります。情報へのアクセス度合いや職務内容を考慮して範囲を限定することが大切です。
Q3. 競業避止義務期間中に最低限の賃金補償をすれば、大丈夫ですか?
A. 裁判所は補償内容の「実質性」を重視します。形だけで実質的な補償とならない場合は無効とされる可能性があります。退職金の上乗せや再就職支援なども組み合わせると、よりリスクを軽減できます。
6.競業避止義務が問題となるケースは弁護士に相談を
退職後の競業避止義務にまつわる問題は、企業の利益や従業員の将来に重大な影響を与えます。特に、顧客の引き継ぎや営業秘密の流出など具体的な損害が発生した場合は、早期に法的手段を検討すべきです。
福岡でお困りの際は、当事務所までご相談ください。併せて、
●就業規則や競業避止義務に関する書面の整備
●損害賠償請求や差止め請求を視野に入れた対応
を講じることができます。
企業側・従業員側ともに、法的に有効な合意を結ぶことと補償や制限の合理性を確保することが重要です。実際の紛争が起きてから動くと手遅れになることもあるため、事前の備えを徹底しましょう。
2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。
※日本全国からのご相談に対応しております。