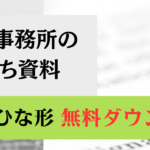1 退職代行とは
近年、労働者が退職の手続きをスムーズに進める手段として「退職代行」というサービスを利用することが増えています。
退職代行とは、従業員が直接会社とやり取りをせずに、第三者(業者や弁護士)を通じて退職の意思を伝え、退職手続きを進めるサービスです。特に、精神的な負担を感じるケースや、未払い残業代の請求を併せて行いたい場合に利用されることが多くなっています。
2 退職代行が使われる主な理由
(1) 退職の意思を伝えるのが面倒、気が進まないため
退職を申し出る際、上司からの引き止めや嫌がらせを懸念し、自分で退職を伝えたくないという理由で退職代行を利用するケースがあります。また、精神的に追い詰められている場合や、対面での交渉が苦手な人も退職代行を選択することが多いです。
(2) 未払い残業代の請求などを併せて依頼するため
労働者の中には、未払いの残業代や給与を請求したいが、会社と直接交渉することに抵抗を感じる人もいます。特に、弁護士が運営する退職代行を利用することで、未払い賃金の請求を適切に進めたいという目的で利用されることがあります。
3 退職代行を通じた退職を、会社は拒否できるのか?
(1) 無期雇用労働者の場合|退職は拒否できない
民法627条1項により、労働者は2週間前に退職の意思を示せば、会社の承諾がなくても退職できます。そのため、退職代行を通じて退職の意思が伝えられた場合でも、企業側が退職を拒否することはできません。
(2) 有期雇用労働者の場合|期間満了時を除き、原則として拒否できる
有期雇用労働者は、契約期間の途中で一方的に退職することは原則として認められません。
そこで、企業側としては、退職の意思表示があったとして、法的に雇用契約は終了しないことを前提として出勤を指示することが考えられます。また、出勤の指示にもかかわらず出勤を拒絶したことにより企業が損害を被った場合には、出勤拒絶と損害の発生との間の因果関係が認められれば損害賠償請求を行うことも可能です。
ただし、契約期間が1年以上の場合や、やむを得ない事情(パワハラ・セクハラ・健康上の問題など)がある場合は、途中解約が認められる可能性があります。
(3) 関連する裁判例
a)中途退職が債務不履行とされたケース
東京地裁平成27年3月31日判決
事案:クリニックに有期労働契約で雇用されていた医師が、体調不良を理由に退職願いを提出した事案。
判決:裁判所は、医師の退職の原因がクリニック側にあった、あるいは、クリニックが退職を了承したとの主張を排斥し、クリニックでの診療及び管理業務等の職務をクリニックの了承なく放棄した医師に債務不履行責任があると認め、後任医師の紹介費用や逸失利益の一部について損害として認定し、医師に賠償を命令した。
b)突然失踪した従業員に債務不履行責任が認められたケース
知財高裁平成29年9月13日判決
事案:無期労働契約の関係にあった労働者が突然失踪し、事業者側が債務不履行に基づく損害賠償請求を行った事案。
判決:労働者は退職するに当たり、所定の予告期間を置いてその旨の申入れを行うとともに、適切な引継ぎ(それまでの成果物の引渡しや業務継続に必要な情報の提供など)を行うべき義務を負い、何らの引継ぎもしないまま突然失踪し、使用者に何らの連絡もしなかったことが債務不履行を構成することは明らかであり、使用者に対して損害賠償義務を負う、とした。
4 労働者に退職代行を使われた企業の対処法
(1) 労働者本人が依頼したものかどうかを確認する
退職代行業者から連絡があった場合、本当に本人の意思で依頼されたものかを確認することが重要です。弁護士が代理している場合は、一般的には委任状を確認することで本人の意思かどうかを確認することができます。弁護士以外の退職代行業者の場合は、本人と直接の連絡を試みることも必要ですが、本人が退職代行を通じてハラスメントの被害などを申告してきているときは、直接の連絡が二次被害とならないように慎重に進める必要があります。
(2) 退職に関するルール・手続きを確認する
就業規則や労働契約に基づき、退職に関するルールを確認しましょう。特に、退職日や引継ぎ義務などが定められている場合は、それに従った手続きを求めることができますし、退職時に提出を求める誓約書などが定められているときは、その任意の作成・提出を求めることとなります。
(3) 退職届の提出・貸与品の返還などの手続きを案内する
退職代行を利用した場合でも、退職届の提出や貸与品(PC・制服・社員証など)の返還を求めることができます。スムーズな手続きのため、必要な書類や手順を労働者に伝えることが大切で、退職代行を通じて案内するときでも、その案内が労働者本人に届いたかどうかを確認するための受領のサインなどを求めるなどして、後のトラブルを防止することが必要です。
(4) 他の労働者の配置転換で欠員をカバーする
急な退職による業務への影響を最小限にするため、他の従業員の配置転換や採用活動を早めに進めることが重要です。特に、退職者が担当していた業務の引継ぎが困難な場合は、迅速な対応が求められます。
また、上記の裁判例を踏まえると、突然に退職を申し出られた使用者側の対応として、職務の引継ぎとして、退職を申し出た労働者に対し、後任が決まるまでの間の業務の継続、成果物の引渡し又は情報提供といったことを明確に求め、それがなされないために損害が発生した時には損害賠償請求を行う可能性があるということを伝えるべきです。
5 退職代行を使われた場合の対応に関する注意点
(1) 退職時の有給休暇の消化について
退職日までに有給休暇の残日数がある場合、労働者は有給休暇の取得を申請できます。会社側は、業務の都合による「時季変更権」を行使することはできますが、通常、退職日までに有給休暇の消化を求められた場合には事業の正常な運営に支障を生じるとしても、これを拒絶することは違法となる可能性があります。退職日以降に有給休暇を取るように求めることは、事業主側の権利としては認められないためです。
なお、退職日の有給休暇の買取りを行うことは、労働者側が希望し、あるいは実質的に強制されることなどなく任意に合意するのであれば問題はありません。
(2) 退職代行の利用を理由とする懲戒処分は困難
退職代行を利用したこと自体を理由に懲戒処分を行うことは、有期労働契約で中途の退職が法的に認められないようなケースでなければ、不当な扱いとみなされる可能性があります。特に、退職の自由は法律で一定程度まで保障されていることなどを踏まえると、退職代行の利用を理由とした不利益な扱いは避けるべきです。
(3) 退職条件の交渉ができるのは、弁護士または弁護士法人のみ
一般の退職代行業者は、退職の意思を伝えることしかできません。未払い残業代の請求や退職条件の交渉は、弁護士または弁護士法人にしか認められていません。そのため、退職代行業者から給与未払い請求などの交渉を持ちかけられた場合は、その業者が弁護士資格を有しているかどうかを確認し、適切に対応することが重要です。
まとめ
退職代行を利用する労働者が増える中、企業側としては、法律に則った適切な対応を行うことが求められます。退職を拒否できるケースとできないケースを把握し、手続きを適切に進めることが重要です。また、未払い残業代請求や退職条件の交渉には弁護士が関与する必要があるため、専門家のアドバイスを受けながら対応することをおすすめします。
退職代行に関するトラブルや対応にお困りの企業様は、福岡の弁護士法人本江法律事務所までお気軽にご相談ください。
2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。
※日本全国からのご相談に対応しております。