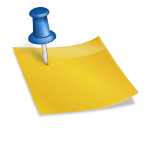1 業務上の理由ではないメンタル不調の取扱い
(1)メンタル不調(メンタルヘルス不調)とは
「メンタルヘルス不調」の定義は、厚生労働省の『労働者の心の健康保持増進のための指針』によると、「精神及び行動の障害に分類される精神障害や自殺のみならず、ストレスや強い悩み、不安など、労働者の心身の健康、社会生活及び生活の質に影響を与える可能性のある精神的及び行動上の問題を幅広く含むもの」と定義されています。
昨今、従業員のメンタルヘルスは、企業にとって重要な経営課題となっています。政府は常時50名以上の従業員を抱える事業所において定期的なストレスチェックを義務化するなど、まずは事業主に対し、従業員がメンタルヘルス不調とならないように職場環境を整えることを求めています。
(2)ストレスチェックの実施
従業員に対するストレスチェックの結果は、検査を実施した医師や保健師から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されます。また、検査の結果、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があるとされた労働者から申出があった場合には、医師による面接指導を実施するように体制を整える必要があります。
(3)メンタルヘルス不調が業務上のものかどうか
職場のストレスが原因でメンタルヘルス不調となった従業員は、労働基準法上の保護の対象となっています。
業務における強い心理的負荷が原因となって精神障害を発症したと認定されると、労災保険の対象となるほか、その疾病による休業の間や、復帰後30日間において解雇することは禁止されます(労基法19条1項)
一方、明らかに職場のストレスなどが原因とは言えないメンタルヘルス不調であっても、使用者が従業員が精神疾患に苦しんでいる状況を把握した場合には、使用者として慎重に対処する必要があります。基本的には、解雇の問題以前に、業務指示の段階でも、メンタル不調を悪化させないように注意すべき安全配慮義務が認められることになります。
2 メンタル不調の従業員を放置するリスク
(1)労働能力に影響がない場合
業務上の理由でないメンタル不調、精神疾患の従業員に対し、どのような対応をするべきでしょうか。メンタル不調となっていることを知った場合、まずは、そのことが労働能力に影響を与えているかどうかを確認する必要があります。
メンタル不調とはいっても、従業員の労働能力、仕事量や仕事の質に影響していないのであれば、不利益な取扱いが行われることのないように配慮する必要があります。
当然ながら、最も不利益な処分である解雇についても、許されないと思われます。
ただし、この場合には、メンタル不調の従業員に対して特段の対応を取らなかったとして、大きな問題にはならないと思われます。
(2)労働能力に影響が生じている場合~合理的配慮の義務
一方、メンタル不調が従業員本人の労働能力に明らかな影響を与えている場合、例えば、原因がはっきりしない遅刻や欠勤が続くとか、作業能率が明らかに低下するといったケースでは、メンタル不調により雇用契約に基づき本来であれば果たすべき労務提供義務が十分に履行されていないということができます。
しかし、その原因がメンタル不調にある場合には、事業主は従業員本人に対し職場で支障となっている事情の有無を確認し、仕事がしやすくなるよう、合理的な配慮をする責務があると定められています(障害者雇用促進法参照)。
この合理的な配慮として、把握した支障となっている事情に応じた改善の措置が必要となります。
例えば、出退勤時刻の調整や、休暇、休職により治療に専念できるようにすること、できるだけ静かな場所で休憩できるようにすること、本人の状況を見ながら業務量等を調整すること、本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要な配慮等を説明することなどが、厚労省の指針には挙げられています。
場合によっては、産業医や主治医への受診やカウンセリングなどの機会を提供して、メンタル不調の悪化を防ぎ、回復を支援することが考えられます。
但し、使用者にとって過重な負担となるような対応は求められていません。あくまで、使用者にとって対応可能な範囲での合理的な配慮が求められています。
(3)合理的配慮を講じることなく放置した場合のリスク
メンタル不調の従業員に対する合理的配慮義務を怠った場合、行政機関からの助言・指導の対象となる可能性がある他、放置した結果、メンタル不調が増悪したり、勤務継続が困難となったりした場合には、使用者が果たすべき安全配慮義務に違反したという理由で損害賠償請求を受ける可能性があります。
3 メンタル不調の従業員を解雇することはできるか
事業者が適切な支援・職場環境の調整といったプロセスを経ても状況が改善しなかった場合に、メンタル不調の従業員を解雇することはできるでしょうか。
(1)解雇は最終手段と考えるべき
従業員のメンタル不調を回復させるために環境を変えるという意味で、退職は一つの選択肢と考えられます。そういった観点で、本人に退職勧奨を試みることは、その態様に気をつける限り許されるでしょう。
しかし、本人の意思によらない解雇という方法は最終手段としてとらえるべきで、他の適切な対応策が尽くされ、効果がない場合にのみ考慮されるべきです。
労働契約法では、解雇は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効」となると定めています(同法16条)。
(2)メンタル不調者に対する解雇の裁判例
【日本ヒューレット・パッカード事件(最二小判平24.4.27労判1055号5頁)】
職場の同僚らによって嫌がらせを受けていると被害申告をしていた従業員が、有給休暇を取得して出勤しなくなり、有給休暇を全て消化した後も約40日間にわたり欠勤を続けたケースで、会社は、就業規則所定の懲戒事由である正当な理由のない無断欠勤があったとの理由で諭旨退職の懲戒処分としました。その後、従業員から会社に対し、上記欠勤は正当な理由のない無断欠勤には当たらず懲戒処分は無効であるとして、雇用契約上の地位を有することの確認と賃金等の支払を求めた事案です。
最高裁は、この従業員が、精神的な不調を抱えて被害妄想に陥っていたことを捉え、実際には事実として存在しないにもかかわらず、約3年間にわたり盗撮や盗聴等を通じて自己の日常生活を子細に監視している加害者集団が職場の同僚らを通じて自己に関する情報のほのめかし等の嫌がらせを行っているとの認識を有しており、上記嫌がらせにより業務に支障が生じており上記情報が外部に漏えいされる危険もあると考えて、自分自身が上記の被害に係る問題が解決されたと判断できない限り出勤しない旨をあらかじめ使用者に伝えた上で、有給休暇を全て取得した後、約40日間にわたり欠勤を続けた、という事実を認定したうえで、このような欠勤は、就業規則所定の懲戒事由である正当な理由のない無断欠勤に当たるとはいえず、上記欠勤が上記の懲戒事由に当たるとしてされた諭旨退職の懲戒処分は無効である、としました。
最終手段として解雇の必要があったか、ということを判断する上で、最高裁は、このような精神的な不調のために欠勤を続けている労働者に対しては、精神科医による健康診断を実施するなどした上で、その診断結果等に応じて必要な場合は治療を勧めた上で休職等の処分を検討し、その後の経過を見るなどの対応を採るべきとして、未だ他の適切な対応策が尽くされたとは見なかったと理解することができます。
4 メンタル不調の従業員に対する対応に迷ったときは
メンタル不調の従業員がいる会社の経営者としては、上記のように慎重な対応が求められることになりますが、最終判断の場面では弁護士などの専門家によるアドバイスは不可欠です。
当事務所は福岡・天神に拠点を構え、企業法務の一環として使用者側の労務問題に長年取り組んできていますので、従業員に対する解雇の是非についても多くの経験があります。緊急性に応じて土日の対応も行っていますので、是非お気軽にお問合せください。
2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。
※日本全国からのご相談に対応しております。