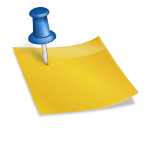1.はじめに
企業経営を行う上で、従業員が業務中に負傷する、いわゆる「労災事故」は避けたい事象の一つです。しかし、従業員の怪我が「本当に労災事故なのか、それとも別の要因によるものなのか」を判断しづらいケースも多くあります。たとえば、就業時間外の活動中であったり、会社の指示による業務ではないが業務と関連があるようなケースなど、グレーゾーンに分類される事例は決して少なくありません。
一方で、実際に怪我をした従業員や、その家族が「これは労災に該当するのではないか」と主張した場合、会社側としては的確に調査・対応を行う必要があります。判断を誤ってしまえば、労災認定のトラブルに発展したり、逆に支給されるべき保険給付を受けられなくなる可能性もあるためです。
本コラムでは、会社側にとって判断が難しい労災事故のケースについて整理し、どのような手続きを踏むべきか、そして万が一紛争に発展した際の対応策や、早期に弁護士へ相談するメリットなどを解説していきます。
2.そもそも労災事故とは?
労災事故とは、労働者災害補償保険法に基づき、「業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡」を指します。簡単にいえば、業務中や通勤途上での怪我・病気等がこれにあたります。ただし、実際に労災かどうかは、以下の二つを満たしているかどうかで判断されるのが一般的です。
-
業務遂行性
-
会社の指揮監督下で仕事をしていたかどうか、またはそれに準じる状況下にあったか。
-
-
業務起因性
-
仕事や作業内容が原因となって怪我や病気が発生したと言えるかどうか。
-
この二つが認められれば、労働基準監督署を経由して労災保険の給付を受けることが可能となります。一方で、私的な行為や単なる偶発的な事故の場合には労災認定が難しい場合があります。会社側としても、この二つの要件を正しく理解し、実態に即した調査を行う必要があります。
3.労災事故かどうか判断が難しいケース
(1) 業務外の活動だが会社の指示があった場合
会社の管理下とはいえ、業務とは直接関係のない行為が原因で発生した怪我の場合、「本当に業務との関連性があるのか?」という判断が曖昧になることがあります。たとえば、社内イベントや親睦会、研修旅行中のアクティビティで生じた怪我などが典型例です。
-
具体例: 新入社員歓迎会の余興を会社主催で行っていた際に負傷した
-
会社側が業務の一環として実質的に指示・管理していたか、それとも任意参加の私的行為の領域が大きいかがポイントになります。
-
(2) 通勤途中に寄り道をしていた場合
通勤途中の事故は基本的に「通勤災害」の対象となりますが、業務と無関係な行為(私的な用事のための大幅な寄り道など)が原因で時間経過が長くなった場合には労災と認められないことがあります。その線引きはケースバイケースであり、従業員本人が当初の通勤経路からどの程度逸脱していたか、私的行為の目的や時間・場所などから総合的に判断されます。
(3) 在宅勤務・テレワーク中の怪我
近年のコロナ禍以降、在宅勤務やテレワーク中の労災事故についても注目が集まっています。自宅で仕事をしている時間帯に発生した怪我・病気が、業務起因性を有するのか、それとも単なる家事や私用によるものなのかは、一見すると分かりづらい場合が多々あります。在宅勤務時にも会社側の管理責任や指示範囲が及ぶのかという点が問題となるため、就業規則や社内規定の整備が欠かせません。
4.会社側の対応のポイント
(1) 事故発生直後の情報収集
労災かどうかの境界があいまいな場合、まずは客観的な事実関係を丁寧に確認することが重要です。従業員や目撃者からヒアリングを行い、当時の状況を可能な限り詳細に把握しましょう。後から「聞いた話と違う」というトラブルが起きないよう、書面化しておくことも有効です。
-
事故が起こった「日時」「場所」「作業内容」の記録
-
当事者以外の「目撃者」「同席者」の証言確保
-
SNS等に関連する記録(飲み会やイベント等の場合は写真や動画など)
(2) 労働基準監督署や関係各所への報告義務を確認
労災事故により労働者が死亡し、または休業した場合には、労働基準監督署への労働者私傷病報告等の提出による報告義務が生じます。たとえ労災かどうか判断が微妙でも、後から報告を怠ったことが明らかになると会社側に不利な状況を招きかねません。
企業としては、労働安全衛生法や労働基準法等に基づき、適切に報告を行うとともに、早期に従業員とのコミュニケーションを図っておくことが大切です。
(3) 自社の就業規則やガイドラインの確認・整備
労災事故を判断する上で、就業規則や安全衛生管理規定が整備されているかが大きなポイントとなります。とくに在宅勤務や事業外活動の取扱いなど、ルールが明確になっていないと、後々のトラブルに発展しやすくなります。
事前に弁護士や社労士など専門家に相談しながら、就業規則や安全衛生マニュアルを整備しておくことが望ましいでしょう。
(4) 保険会社との連携
会社側として労災の可能性を考慮したとき、もし個別に「業務災害総合保険」や「使用者賠償責任保険」に加入している場合は、速やかに保険会社へ事故報告を行います。保険会社からは事故対応のアドバイスを得たり、損害賠償請求が生じる場合のサポートが受けられることもあります。
会社側のリスクマネジメントの一環として、保険加入の確認や連携を怠らないようにすることが重要です。
5.トラブルに発展する前に弁護士に相談するメリット
労災事故が起こると、従業員との間に意見の相違が生じることがあります。従業員側は「会社の指示で行った作業中の怪我だから労災事故だ」と主張し、会社側は「そこまで明確に業務とは認められないのでは」と考えるケースが典型的な例です。このような「労災事故かどうか」のトラブルを放置していると、従業員のモチベーション低下や、労働基準監督署とのやり取りが長期化し、企業イメージの低下にまでつながりかねません。
ここで、早期に弁護士へ相談するメリットを整理しておきましょう。
-
正確な法律判断とリスク管理
-
労働基準法や労災保険制度に精通した弁護士であれば、業務遂行性・業務起因性を踏まえた的確な見解を示すことができます。
-
会社側にとって最適な対応策を提案し、不要な賠償責任やトラブルの長期化を防止できます。
-
-
紛争予防のための書面作成や手続きサポート
-
弁護士のアドバイスのもと、ヒアリング内容を文書化したり、就業規則の改定を行ったりすることで、後から生じる証拠不足や誤解を最小限に抑えられます。
-
労働基準監督署や保険会社との連携もスムーズに行えるようになります。
-
-
従業員側との交渉窓口としての役割
-
従業員との話し合いが難航する場合、弁護士が間に入ることで冷静かつ適切な交渉が可能になります。
-
会社側としては、従業員に対する配慮は欠かせませんが、過度な譲歩をしないようバランスをとる必要があります。弁護士が第三者の専門家として関与することで、双方にとって納得しやすい形に落とし込みやすくなります。
-
6.労災問題を未然に防ぐためのポイント
労災事故におけるトラブルは、事前の予防策で大きくリスクを減らすことができます。労災事故を防ぐ対策だけでなく、万が一発生した際に円滑に対応できる仕組み作りが求められます。
-
危険箇所・工程の見直しと安全教育
-
現場作業や工場などであれば、特に危険な工程や場所を定期的に点検し、安全対策をアップデートする。
-
オフィスワークであっても、在宅勤務など多様化した働き方に合わせた注意喚起が必要。
-
-
就業規則・社内規定の周知徹底
-
業務範囲や通勤災害の定義などを従業員に理解してもらうよう、研修や説明会で周知する。
-
親睦会やイベント等についても「会社主催」の扱いと「私的行為」との線引きを明確化する。
-
-
発生時の報告体制の整備
-
怪我や事故が起きた際の報告フロー(誰に報告し、どのように対応を進めるか)をマニュアル化する。
-
上長だけでなく、人事・総務部門や安全衛生担当者、必要に応じて弁護士に速やかに共有できる仕組みを作る。
-
-
保険契約の見直し
-
会社独自で加入可能な業務災害総合保険や使用者賠償責任保険などが、万が一のときに十分な補償をカバーしているか確認する。
-
条件や補償範囲を定期的にアップデートし、最新の就業環境に合った内容になっているかチェックする。
-
7.まとめ
従業員が怪我をした際、それが「労災事故」に該当するかどうかの判断は、業務遂行性や業務起因性を丁寧に検討する必要があります。会社側としては、一度「労災かどうか」の結論を急いでしまうのではなく、事故直後の情報収集やヒアリングを徹底し、適切に労働基準監督署や保険会社へ報告する体制を整えることが重要です。
さらに、難しい事例や従業員との認識に相違があるケースでは、早い段階で弁護士に相談することがリスクを最小限に抑える秘訣となります。弁護士を介することで、会社側の対応が法的に適切かどうかを確認でき、従業員にも納得感のある説明を行える可能性が高くなります。
本江法律事務所のように企業法務や労働問題に精通した弁護士であれば、労災事故に関する知見を活かして、事前の予防策から紛争解決までのサポートが可能です。**「労災事故」「会社側」「弁護士」**といったキーワードでお探しの際は、ぜひ専門家にご相談いただき、早めの対策を講じていただければと思います。
【免責事項】
本コラムの内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法律問題に対するアドバイスではありません。実際の事案については、必ず弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談のうえ、対応方針を決定してください。
2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。
※日本全国からのご相談に対応しております。
-
弁護士法人本江法律事務所 弁護士 本江 嘉将https://www.motoe-law.jp/author/motoe-law/
-
弁護士法人本江法律事務所 弁護士 本江 嘉将https://www.motoe-law.jp/author/motoe-law/
-
弁護士法人本江法律事務所 弁護士 本江 嘉将https://www.motoe-law.jp/author/motoe-law/
-
弁護士法人本江法律事務所 弁護士 本江 嘉将https://www.motoe-law.jp/author/motoe-law/